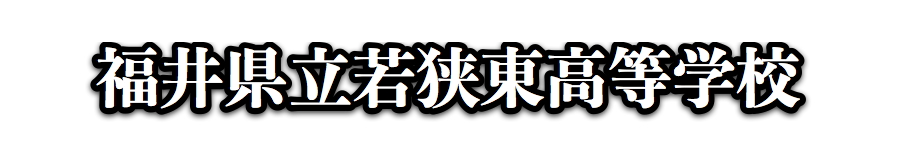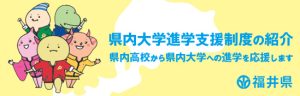1年生では全員が「農業と環境」や「測量」などの科目で基本的な専門科目の学習をします。2年生からは興味・関心・希望進路などに合わせて2コースにわかれ、より深く専門科目を学びます。
次の専門科目は、地域創造科全員が学習します。

農業と環境(1年生)
作物や野菜、草花の栽培学習を行っています。植物の生育と天候にもよりますが、栽培学習を通して農業の基礎・基本について学習しています。
写真は、5月の田植え実習と11月にサトイモの収穫をしたときの様子です。

測量(1年生)
構造物の基礎地盤の高さの測定や地図を作るための基礎など、測量の基本的な知識や技術を学び、社会での必要性を理解します。

農業と情報(1・2年生)
農業に関する情報について、多様なメディアを組み合わせてコンテンツを制作する方法や、発信する方法、データ分析などを学習します。

農業経営(2年生)
農業経営について、仕組みや経営管理などを一貫して学習します。簿記の学習もします。
2年次からは、「食農創造コース」と「地域開発コース」に分かれて、それぞれの専門科目を学習します。
食農創造コース
野菜や草花等の植物の生産から食品加工・調理、販売までの6次産業化に対応した内容を学習します。地域の農業生産や食品に関する学習を通じて、農業・食料関連産業を担う人材を育成します。

野菜(2・3年生)
野菜(施設栽培、露地栽培)の生産について、播種から出荷までを一貫して実習を含め学習します。

草花(2・3年生)
草花(苗もの、切り花、鉢もの)の生産について、播種から出荷までを一貫して実習を行いながら学習します。

栽培と環境(2年生)
気象や土壌などの栽培植物の育成環境や、環境に配慮した栽培管理の方法について学びます。日本農業技術検定3級の資格取得にも取り組みます。

地域資源活用(2年生)
地域の農作物を活用した事例について学習します。本校では薬用植物「コウギク」を若狭地域での産地化を目指した取り組みを行っています。写真は、コウギクのさし芽による繁殖実習をするところです。また、薬用植物コウギクの粉末を活用した商品開発についても学習しています。

フードデザイン(2年生)
フードデザインでは、食生活に関する基本的な知識と技術を習得し、食事を総合的にデザインする能力と態度を養っています。

食品製造(3年生)
食品製造について、農産物の加工や食品衛生、品質管理などを一貫して実習を含め学習します。

課題研究(3年生)
農業に関する課題を設定し、その課題を解決するための方法や計画を立てるとともに、解決策を探求していくことを実習を含め学習します。取り組んだ内容をまとめ発表をします。
地域開発コース
農業土木施工や測量の基礎・基本を学び、国家資格の合格を目指します。さらに、地域の環境についても学習します。地域開発に貢献できる知識・技術を身につけた技術者を育成します。

農業土木設計(2・3年生)
農業土木構造物の計画・設計に必要な、基本的な知識や技術を学び、製図やCADを学習します。

農業土木施工(2・3年生)
土木工事に使用する土木材料の実験・実習を通して知識を学びます。コンクリート工事や建設機械、施工計画や工事管理について学習し、2級土木施工管理技士補の資格取得を目指します。

測量(2年生)
基本的な知識を活かし実習を通して、角度や距離の測定など専門的な知識や技術を学びます。また、国家試験の測量士補取得を目指します。

課題研究(3年生)
里山や地域の植物の研究調査を通して、自然環境に関する知識を学びます。また、農業クラブの測量競技大会での上位入賞を目指して、測量技術を向上させます。